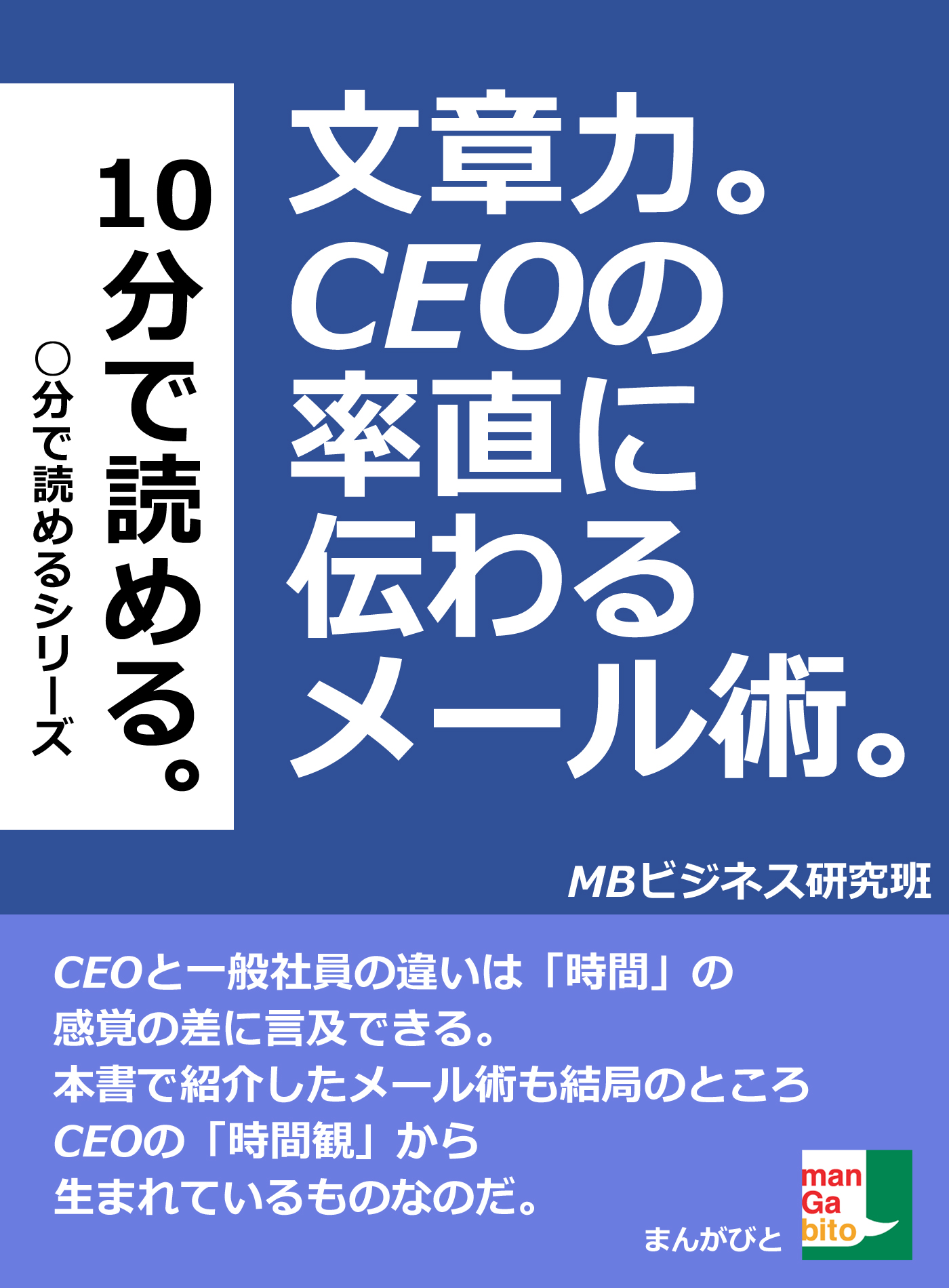Contents
まえがき
どんな会社でも勝手に収入が入ってくるような、半自動で利益が出るような仕組みがほしいはずだ。毎月毎月待っていれば自然と収入が入る。税金のようにユーザーから代金回収できる。そんな状況を望んでいるだろう。
もうかる仕組み、それは、どの会社も求めてやまないものであるが、反面、それが会社を悪くする場合もある。
本書では、そのパラドックスを、せっかくもうかるのに、それが会社を悪くしてしまうという、不思議な矛盾をひもといていこうと思う。それによりもうかる仕組みを持っている会社が陥りやすい、ビジネスの袋小路を突き止め、予防策となるような思索がしたい。そして読者の皆様の会社を自己矛盾の落とし穴から救うことができるだろう。
成功とは、あまりに甘い果実だ。一度食べてしまえば、忘れるには甘すぎる。
2つのグループ
どんな会社も、もうかる仕組みを創りださなければ生き残っていけない。利益が会社を存続させる。しかし、その仕組があまりにもうまくいってしまうと、労働が非常に簡単になってしまう。簡単になった労働になれた人たちは、もう二度と新しいもうかる仕組みを作ることができない。
もうかる仕組みを作るのは非常に大変なのだ。もうかる仕組みがすでにあるのだから、新しい仕組みを作る必要はないと感じるかもしれない。もし永遠に、今の仕組みが有効なのだとしたら、その通りだ。しかし、永遠に勝ち続けるビジネスはない。グローバル企業という概念が登場して、まだまだ日が浅いため結論は出ていないように見えるのだが、無限に生き続ける人間がいないことと同じように、無限に生き続けるもうかる仕組みも存在しない。
もうかる仕組みが会社を殺すということを、みなさんに信じてもらうためには、社内の人たちを2つに分けるとわかりやすいだろう。
一つ目は、創業者グループだ。
これはどういったグループかというと、文字通りの創業者も含み、創業者的な役割をした人たちは全員含まれる。社内ベンチャーを立ち上げた若手社員がいたら、そういった人も、このグループだし、そこまではっきりと新規事業でなくても、新しいもうける仕組みを作っている人たちは全員、ここに分類できる。ちなみに、このグループに含まれる人たちは雑多で学歴や経歴が様々な人たちが入り乱れるのも特徴だ。
二つ目は業務遂行グループだ。
このグループは、新しいもうかる仕組みを創りだすというよりは、出来上がった仕組みを忠実に実行する。マニュアル通りにしっかりと業務を行う能力が高く、総じて高学歴であれば、あるほど、この能力が高い。より強力なもうかる仕組みを持っている会社は、給料をたくさん出せるので、高学歴の学生を採用して、業務遂行の任務に当たらせる。
会社のなかは、この2つに分けることができる。もちろん、2つのグループに跨がる人もいるし、グループを移る人もいる。会社は、この2つのグループのバランスでなりたっている。
さて、ここで少し考えてほしい。もうかる会社、利益が出る会社は、どちらのグループが大きいだろうか。優良企業と呼ばれる会社の社員は、よりどちらのグループに所属しているだろうか。
業務遂行のグループが大きい会社が、利益が出ている会社だし、利益の規模を大きくしようとすると、このグループが大きくなりもする。
実は実際に金を稼いでいるのは業務遂行グループだけなのだ。創業者グループは、もうかる仕組みを考えているだけで、実際に、そこから代金の回収を行うわけではない。だから、良い仕組みを作ったのなら、あとは業務遂行グループが、それを回転させながら大きくしていくわけだ。まず、この2つのキーワードがあることを覚えておいてほしい。
コストカットの罠
会社組織は一度出た利益を継続して計上したいと思っている。ここに落とし穴がある。どんなビジネスでも、良いときと悪いときがあるのだ。それでも常に利益を成長させようと思ったら、コストカットを行わなければならない。
まずは無駄からカットしていくだろう。本当の無駄であれば、これはもちろん問題ない。しかし、それでは足りない場合もある。その場合に創業者グループの人件費をカットするケースがほとんどだ。創業者を辞めさせるなんてみたことがないと思うだろう。たしかに社長だけは別格だ。しかし役員や創業者グループに属する社員に関してはコストカットの対象になっている。
どういった方法でコストカットするのか。圧倒的に人数の多い業務遂行グループは、人が自主的に辞めるということが多い。そのさいに、新たな人材を補充で採用しないとしよう。この場合、コストカットされているのは業務遂行グループに感じるが、実際は業務が回らなくなるので、創業者グループの若手社員から順番に業務遂行グループに移行していくことになる。組織の異動などというわかりやすい形でなく、陣頭指揮という名目だったりするからわかりにくいが、とにかく現場で仕組みを回すための業務につき始める。さすがに経営者だけは、この流れで現場に入ってしまうことは少ないが、ほとんどの社員は現場に引っ張られる。
しかし、それでも、みんなで働けば予定の利益額はあげられる。
翌年の利益の目標は今年よりも高くなる場合が、ほとんどだから、さらに、みんなで現場に出なければいけなくなる。そして、この状態が慢性的になるのだ。
ただ、ここまでで会社が駄目になるような要素はない。目標の利益が達成できているのだから、文句ない結果だ。しかし、崩壊の足音は、少しずつだが近づいている。
プロダクトライフサイクルの絶対性
商品には、4つのライフサイクルがあると言われている。
まず導入期だ。
商品が顧客に認知されはじめる段階だ。このときにはまだ利益は出ていない。
2番目に成長期だ。
認知が身を結び急激に売上が増加し利益が出るようになる時期だ。創業者グループは、ここまでが仕事だ。売上は前年比の数十倍、数百倍ということもある。
3番目に成熟期だ。
売上が安定し、利益は最大化する。業務遂行グループは、ここで大活躍する。売上は前年比2割りまし3割りましあたりで推移しながら、ある時点から下がり始める。
4番目に衰退期だ。
その商品は終わりに近づいている状態で、いくら頑張っても現状維持も難しいという状況だ。
これは商品のライフサイクルだが、ビジネスモデルのライフサイクルも最終的に、お客様に有形、無形の商品を提供するという意味で同様であり、この理論は当てはまる。
そしてもうかる仕組みがあるというのは成熟期の状態ということだ。
そして、このもうかる仕組みがある状態。成熟期の状態がながい会社は非常に危険だ。本書のタイトルであるように、「儲かる仕組みが会社を殺す」となり兼ねない。
どんなにがんばっても、いつかはビジネスモデルは衰退するのだ。しかし、一度知った甘すぎる果実、もうかる仕組みを手放したくないために、創業者グループを徹底的に縮小して、業務遂行グループを拡大する。そうすれば、多少衰退は先延ばしにできるのだが、根本的な解決ではない。根本的に解決するには、新しいビジネスモデルを成長期に到達させて、組織が移動できる先を作ることなのだ。
誰がやるのか。もはや、身動き取れず。
ここで一つ例をあげてみよう
老舗のスーパーであった武田スーパーマーケット。地元の人たちから愛されて創業60周年を迎えた。創業者である、武田信一郎は、もともと町の酒屋だったのだが、いろいろな業態を模索しているうちにスーパーにいきついた。ある程度成功し店は3店舗、従業員はパートを含め150人を数えるほどになった。信一郎はすでに10年前に亡くなり現在では息子の勝一郎があとを継いでいる。
60周年を迎えた同社であるが、祝っているような気分ではなかった。近所に大手スーパーが相次いで進出。経営はかなり厳しくなっていた。信一郎生存中には、新規事業の立ち上げを繰り返す若手、中堅どころの社員グループがあったのだが、彼らも今は、本業であるスーパー事業の立て直しに尽力している。衰えは緩やかになったのだが、営業利益は減少を続けていた。
このビジネスはダメだ。新規事業しかない。そう思って、なにか新しいことをはじめようと、以前の新規事業立ち上げグループに話を聞いてみたが、誰もがスーパーの既存の業務にどっぷりと浸かってしまい新しいアイデアすら出てこない。多少なりとも良いアイデアが出ても、誰がやるかというところで、みんな顔を見合わせてしまう。勝一郎は、
「みなさんは信一郎の下で散々、新規事業をやってきたでしょう。」
と、言っても、
「もう10年も前ですから、今は、挑戦する気概がありません。」
というように、任せてもうまくいきそうにもない。
そんな中で、晩年の信一郎と最後の事業を一緒に担当していた、当時若手社員だった真田が口を開いた。
「実は10年前途中までうまくいっている事業がありました。」
勝一郎が社長に就任した際に、新規事業は無駄だと考え、その労力をすべて既存事業に向けた。その結果、武田スーパーマーケットは過去最高益を3年連続で記録した。その後は、大手スーパーの進出により、現在の状況なのだが。
「それは、どんな事業だ」
「宅配クリーニングサービスです。1周間に一度洗濯物を取りに行って、その場で預かっていた洗濯物を渡すのです。これを洗濯物の量により月額制で行いました。」
「よし、さっそくそれをやろう」
そう考えて、近所のマンションの住人に営業をかけはじめたのが、そこで驚くべきことがわかった。別の会社がまったく同じサービスを展開していて入り込む余地がなかったのだ。相手はすでに規模の経済を手に入れていて、サービスの価格も武田が提示できる金額の半額だった。
その会社は、ウィークリーランドリーという企業で、創業5年目であった。すでに一部上場し、世間では知る人ぞ知る存在だった。
もうかる仕組みが会社を殺す
もうかる仕組みがあると、人間はそれに甘んじてしまって、新しいもうかる仕組みを作ろうとしなくなってしまうのだ。マイクロソフトやトヨタくらい盤石なものを作れたのならまだしも、ほとんどの会社のもうかる仕組みは大抵脆弱なものだから、それを守るために必死に努力しても結局は、プロダクトライフサイクルの法則で行き詰まるのだ。
それでも、その仕組みを守ろうとしてしまう人間の心理に落とし穴がある。
勝一郎は、父親から引き継いだ「もうかる仕組み」を最大化した。未来のもうかる仕組み作りを放棄してまでも、業務遂行グループを手厚くしたのだ。創業者である、信一郎にはわかっていたのだ。スーパーマーケットというもうかる仕組みは続かない。そのときに会社が死なないように新しい仕組みを作らなければいけないと。
実は会社が一番強いときは、仕組みを作ろうと、どうにか、こうにか足掻いているときだ。そのなかで、少ない利益でなんとか生活しながら、「もうかる仕組み」を探している。
しかし、それを経験しなかった人たちは、その仕組が永遠と続くような気がするし、その仕組の枠の中で頑張ろうとする。それが結局は会社を殺すのだ。
では、どうすればよかったのか。
現在の「もうかる仕組み」による恩恵をまったく受けない創業者グループを、常に会社のなかに用意しておこう。
そして、そこから生まれてくる仕組みに、うまく業務遂行グループの従業員を移行させつつ、古い仕組みは縮小していく。この話でいけばスーパーマーケットを縮小しながら、クリーニングの事業に移れればよかったのだ。
「もうかる仕組み」という成功体験が、会社を殺してしまうことはままある。あなたが創業者グループなら、常に、このことを意識してほしい。
あなたが、業務遂行グループなら、会社の中に創業者グループがどのくらいいるか、よく眺めてみよう。彼らが元気があるようなら10年後も大丈夫だ。見かけない、あるいは元気がないようなら、かなり危険だ。転職を覚悟しておこう。
あとがき
グッドはグレートの敵という言葉がある。
人間は、そこそこの成功をしてしまうと、そこにあぐらをかいてしまって、もう一度、若いころのように大変な努力をできなくなくなるのだ。一度作ったものを、しゃぶり尽くすように生きていたら、いつかは行き詰まるのは必然で、そんなことは考えれば、わかるはずなのだが、自分のこととなるとなかなか気が付かない。
成功体験が首を締めるというのは、会社でも個人でも同じだ。個人にしたって、一度うまくいったやり方を、どうしても繰り返そうとする。外部要因や内部要因が変わっているのに方法論が同じで成功すると思ってしまうのだ。
個人にしても、どれほど成功しても、また新しい成功法則を作りだなければならない。それは、ビジネスを引退しても人生が続く限りは繰り返される。それは人生の厳しさでもあるが、同時に面白さでもあるはずだ。
いつまでも若々しい心で挑戦し続けよう。
少しでも本書がお役に立ったようでしたらシェアをおねがいします。