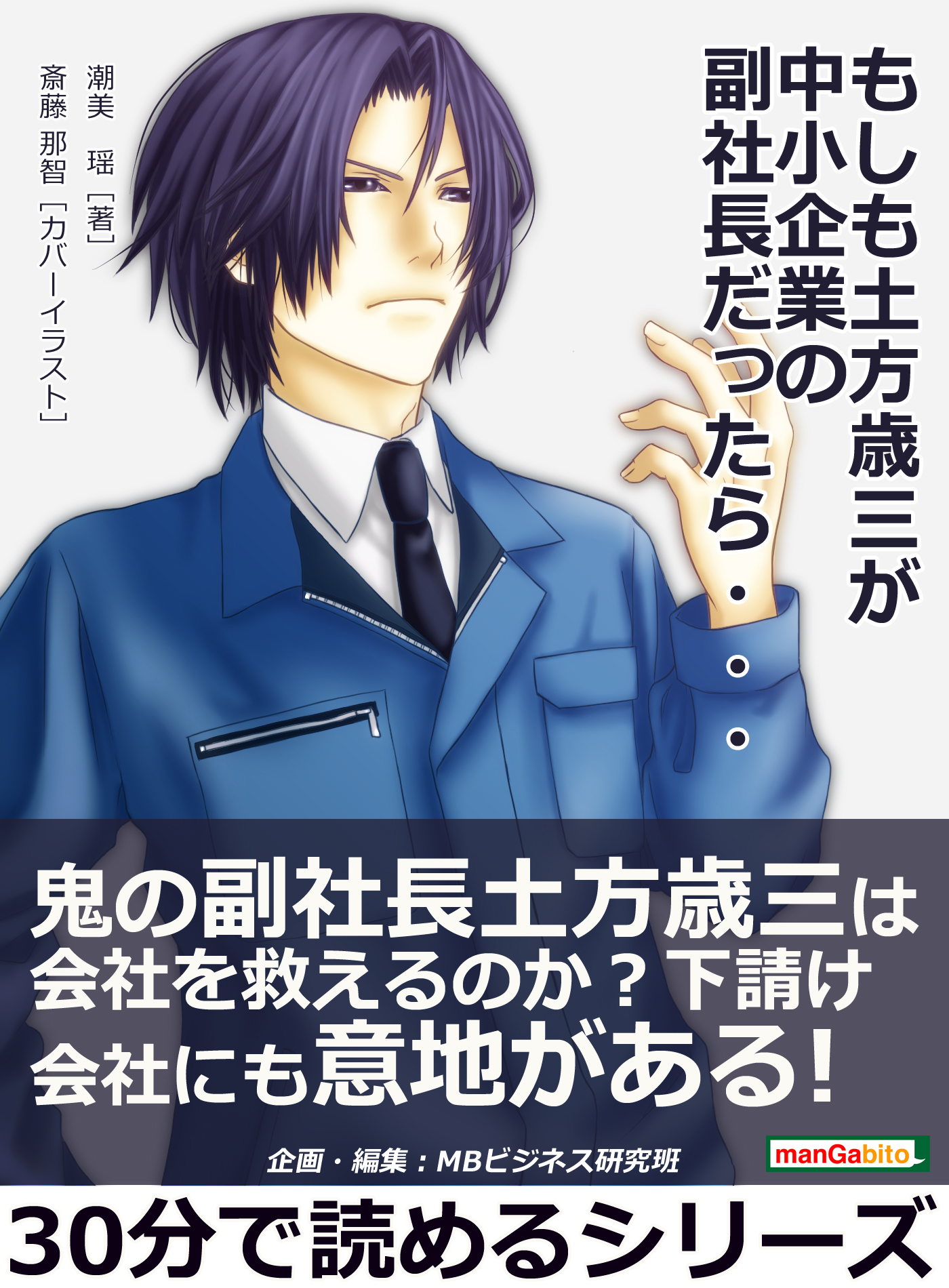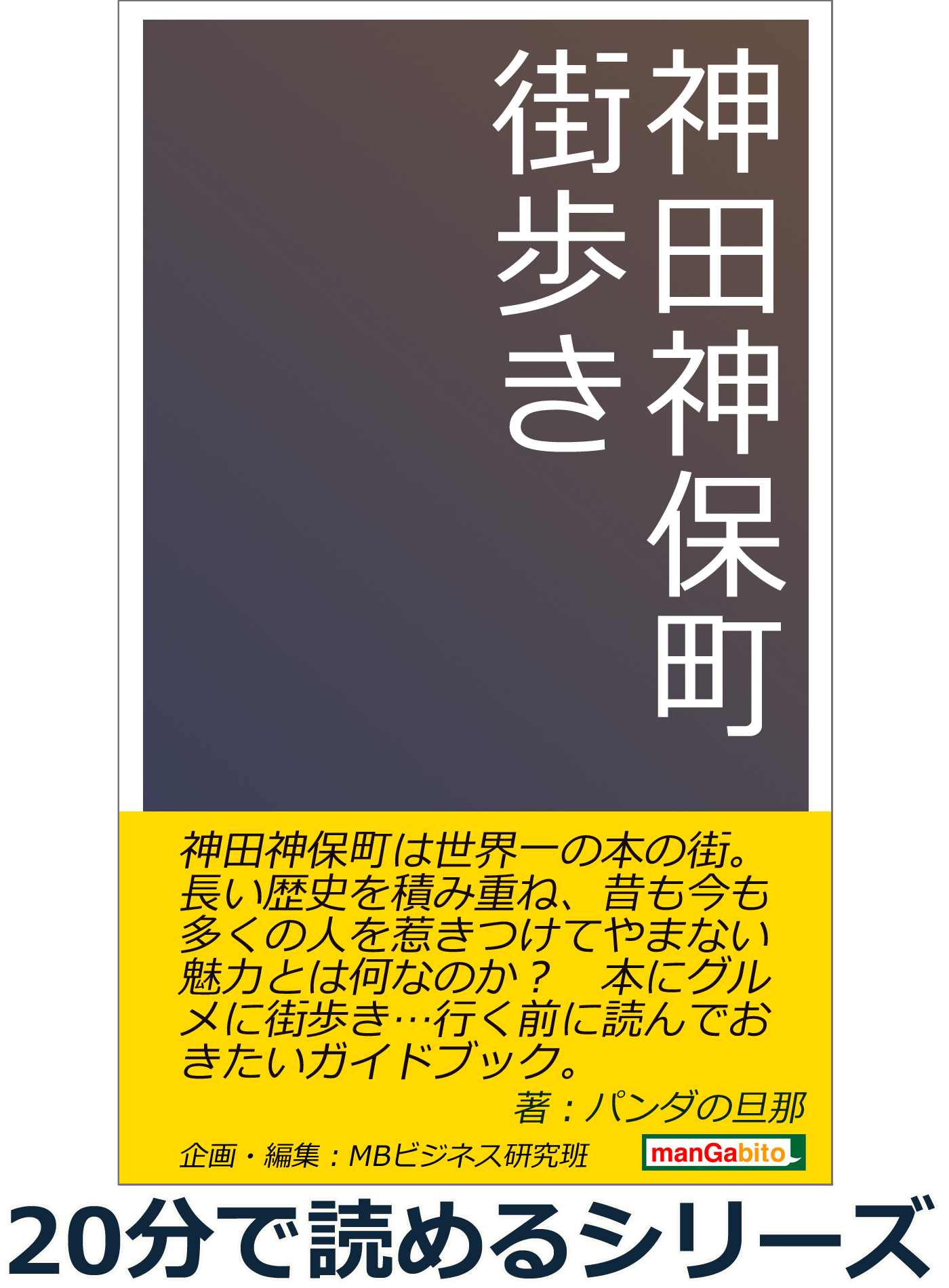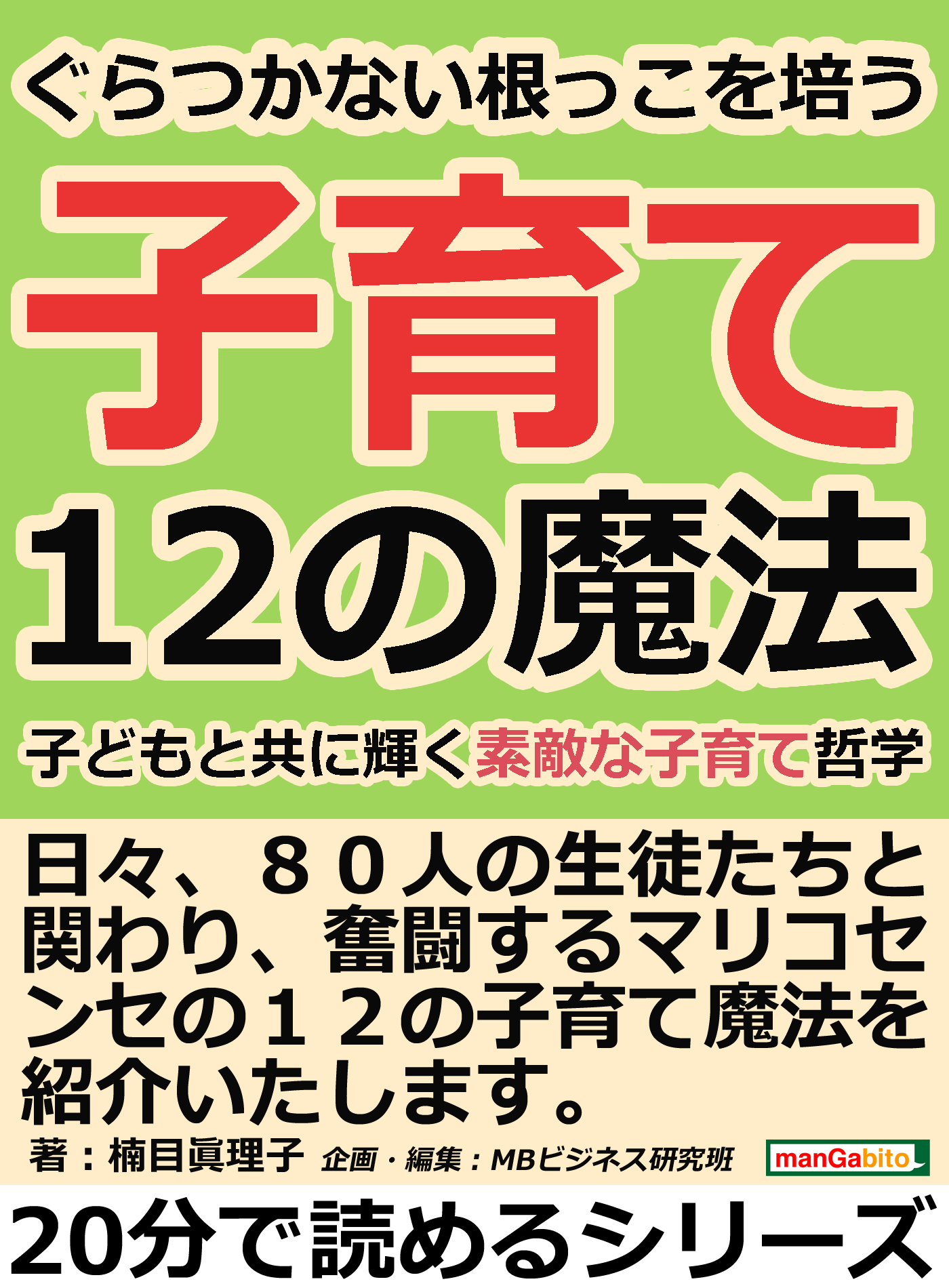ラストプレゼント。
10分で読める45歳サラリーマンは、つい涙してしまう物語。電車内で読むのは危険。
半分無料公開中!当社では現在は取り扱っていない物語作品ですが、こちらはよく売れましたので半分無料公開中です。
第一章「クリスマスイブ」
街の至る所に赤と白の衣装を纏ったキャラクターが溢れている。それとセットになって黄金色に輝くベルや、青々とした柊の葉が飾られている。毎年十二月の後半になると、誰しもが皆取り憑かれたかのように「メリークリスマス」と異国めいた呪文を唱える。どうやら、今年も気が付かないうちにその日がやってきたらしい。
「メリークリスマスだとさ。駅前でバイトの姉ちゃんがケーキのチラシ配ってたぞ」
「へぇ……」
手汗ですっかりしわしわになったチラシを見せてくる年寄りを横目に、冬海銀司(ふゆみぎんじ)は酷く無感情な相づちを打った。
「なんだおまえさん、クリスマスとやらが嫌いか?」
銀司の反応の悪さを悟ったのか、年寄りはチラシから顔を上げて銀司の顔を覗き込んできた。バチッと目が合う。黄色く濁った瞳と、ぼさぼさになってしまった白髪交りの頭、それに追い打ちをかけるかのようにボロボロの作務衣。それらがこの年寄りの全てを著しているかのようで銀司はサッと目を逸らす。
「嫌いってわけじゃない。ただ、どうでもいいだけだよ」
「つれんのー……まぁ、わしらみたいなホームレスには縁もゆかりもない話しか」
言いながら年寄りはチラシを小さく丸めると、すぐそばのごみ箱に投げ捨てた。カサッと乾いた音がして、丸まったチラシはごみ箱の中へと吸い込まれていった。
ホームレスと呼ばれることに抵抗がなくなったのはいつだっただろうか。数年前まではクリスマスだって自分にとっては一大イベントだったような気がする。街中が徐々に電飾で飾り付けられていく様子を、通勤中や営業での外回り中に眺めていたはずだ。あの頃は、この季節になるとクリスマスプレゼントのことばかり考えていたように思う。でも、それも今では遠い記憶の泉に沈んでしまっている。自分があの頃どういう生活をしていたかを思い出したくはないと銀司は深くため息をついた。
十二月二十四日、今日は世間一般で言うクリスマスイブという日だ。大きな駅の横にあるこの公園にもその気配は充分に届く。近くのデパートや店からは軽快なクリスマスソングが漏れ出しているし、買い物袋を抱えた主婦達は入れ替わりにケーキ屋に吸い込まれていく。普段は不良少年達がたむろしているコンビニの入口も、今日ばかりはケーキ販売のためのスタンドが設置されていて、たまり場としての役目を果たしていない。
「クリスマスなんて、ホームレスには侘びしいだけじゃの」
「そうだな」
「こんな日は残飯が少し豪華になるくらいかの……時におまえさん、その黒いコートはどこで拾ったんだ? やけに素敵に見えるぞ」
言いながら年寄りは銀司のコートを軽く撫でた。この年寄りとはつい最近知り合った。残飯を拾い歩いていたらこの界隈に流れ着いたらしい。こうやって昼間にたまに会話するのが日課になっていた。
「昨日の夜に粗大ゴミ置き場に放置されてたのを頂いたんだ」
「ほぉ! そりゃ良い拾い物をしたな。おまえさんの黒い髪によく似合ってるぞ」
言われて、銀司は自分の黒髪を少しつまみ上げた。そういえばしばらく髪を刈ってない。目にかかりはしないが、心なしか鬱陶しくなってきた気がする。
「こぎれいなコートを着てると、到底ホームレスには見えんぞ」
「そりゃどうも」
「そういえば、知ってるか? 最近人を捜してホームレスに接触してくる女性がおるそうじゃよ」
「人捜しねぇ。ホームレスに聞いても見つからないだろうさ」
「どうかのぉ……見つかるとええの」
「まぁ、俺達には関係のないことさ」
そう答えると銀司はその場から立ち上がった。時刻は昼過ぎだ。そろそろ夜に備えて食料を探しに行かないといけない。冬場の夜の冷え込みは行動する気力さえも奪ってしまう。
「もう行くのか?」
年寄りが首を鳴らしながら問う。
「ああ、じゃあな。良い夜を」
囁くような声でそう言うと、銀司はその場を離れた。
***
「……寒い、腹減った」
すっかり暗くなった駅前のベンチで銀司は手に息を吹きかけながら呟く。聖夜だというのに今日に限って残飯が確保出来なかった。目の前を通り過ぎていく人々は皆プレゼントを持っていたり、誰かと待ち合わせをしたり、幸せそうだ。
それに比べて自分は、と銀司は思う。ゴミを漁りすぎて硬くなった指先が余計に惨めだ。何でもいいから、暖かい場所へ行きたい。そう思った銀司がベンチから立ち上がろうとした時だった。突然、声が降り注いだ。
「こんばんは」
ビクッとして顔を上げる。知り合いの年寄りとは違う、澄んだ綺麗な瞳が見えた。
「え、君は……」
「突然、ごめんなさい」
にこっと微笑んだのは、見た事もない女の子だった。肩まである黒くて綺麗な髪の毛をハーフアップにして束ねている。黒いセーターと真白いスキニーズボンが印象的だった。しかし、こんな子が一体自分に何の用だというのか。
「俺に……何か?」
「えっと私、おじさんとお話がしたくて」
話しかけちゃいました、と女の子が言う。なんだこいつは、と銀司は率直に思った。
「それはおかしいことだ。俺と会話をしても何のメリットもないだろ」
「お話ししたいなって思うのが、おかしいですか?」
「おかしい。第一俺はホームレスだ……皆汚いと笑うぞ」
わかっていても、自分でその単語を口に出すと妙に心が痛んだ。そんな銀司の手を、ふいに暖かい物が包み込んだ。ギョッとして見ると、目の前の女の子が、「そんなことないです」と言いながら銀司の手を握っていた。突然の行動に、どきっと胸が脈打った。
「な……」
動揺する銀司の手を女の子はさらに優しく握ると、柔らかい声色で一言こう告げた。
「ラーメン、食べに行きませんか?」
「へ?」
銀司がそう声をあげるのと女の子が腕を引っ張るのは、ほぼ同時だった。
第二章「屋台ラーメン」
「大将さん! ラーメン二人前ね!」
はいよーという威勢の良い声が響いたと思いきや、ものの三分程度で二人前のラーメンが目の前に現れた。銀司は思わず生唾を飲む。いや、食い意地を張らせている場合ではない。突然見ず知らずの自分をラーメンに誘うなんて、この子はどうかしている。
「さ、食べましょう? ここの屋台ラーメン美味しいんですって」
なんて言いながら、女の子は美味しそうにラーメンを食べ始めた。ふーふーとラーメンに息を吹きかけるたびに、白く外気が浮かび上がる。
「…………」
こんな女の子にラーメンを奢って貰っていいものか、銀司は悩む。見るところ女の子は十八歳か十九……いや、二十歳を超しているのか。とにかく若いことは間違いない。もしかすると学生で、ホームレスを助けましたと就職活動の自己アピールのネタにでもするつもりなんだろうか。考えれば考えるほどにわからなくなる。
「どうぞ、遠慮しないで食べてください」
なかなか食べようとしない銀司に気が付いた女の子が、にっこり笑って器に割り箸を乗せてくれる。
「……ありがとう、いただくよ」
ラーメンの誘惑には勝てそうにない。女の子が自分を誘った理由は不明だが、現に腹は減っていた。据え膳食わぬは男の恥……この場合少々意味合いは変わってくるが、有り難く頂くとしよう。銀司は割り箸を割って、ラーメンを勢いよく啜った。残飯ばかりで温かい食べ物は久しぶりだった。熱い麺と汁が冷え切った身体中に染み渡る。
「美味いな」
素直な感想が零れた。
「ええ、美味しいですね」
女の子が答える。
「こんなに美味いラーメンを食ったのは、ホームレスになる前が最後だったっけな……」
ふと、無意識にそんな言葉が口をついてでた。
「おじさんは、どうしてホームレスになってしまったんですか?」
「……たいした事じゃないよ。会社が倒産しちまって、家族にも逃げられたっていう、よくドラマなんかである展開だよ」
自重気味に笑う。ご飯を奢って貰ったんだ、少しぐらい身の上話を聞かせてやっても良いと思った。銀司はラーメンを食べながら、そっけなく話しを続ける。
「俺には、妻と息子がいた。昔は仲良くやっていたんだが……給料が悪くて段々妻との他愛ない喧嘩も増えていった。そんな時、会社が倒産してな。そのことを切り出せなくて、しばらくは会社に行っているフリをしてた。だけどやがて妻に全部ばれて、ある朝目が覚めたら、誰もいなくなってた」
「…………」
女の子は、黙って銀司の表情を見ていた。
「家賃も払えなくなって、気が付いたらホームレスってやつになってた。みっともないだろ? 今日なんて聖夜だってのに、女の子にラーメン奢って貰ってんだからな」
言葉に詰まりそうになった。全ては自業自得なのに、改めて口に出すと悲しくて、思わず涙が零れそうになってしまった。グッと口をむすんで堪える。
「……それは、辛かったですね」
女の子の手が伸びてきて銀司の手を握った。さするような、優しい手つきだった。
「ひとりぼっちで、寒かったですよね……」
「平気さ、もう慣れっこだ」
鼻をすすり上げて、残りのラーメンを勢いよく啜る。こんな女の子の前で号泣したらそれこそ後世まで語り継がれてしまいそうだ。銀司はごまかすように話題を切り替えた。
「君こそ、どうして俺をラーメンに誘ったんだ? ホームレスだぞ、俺は。就活のネタにでもするつもりかい?」
この際ズバッと聞いてやれと、先程脳内で浮かんだ事を投げかけてみる。だが、女の子はきょとんとしたまま首を横に振った。
「違いますよ?」
「え、じゃあ何でだ?」
「理由なんてないですよー」
「嘘だな、絶対何か深い理由があるだろ」
「深い理由が必要なんですか?」
「いや、そうじゃないが……」
「ならいいじゃないですか、ね?」
すっかり女の子のペースだ。上手いように言いくるめられてしまった。理由がないというのも納得行かないが、嘘をついているようにも見えない。
銀司達のやり取りを目の前で見ていた大将が、ニヤニヤしながら「あんたに惚れたのかもしれねぇぜ、このお嬢ちゃん」と冷やかしてきた。何を馬鹿なことを。どこの世界に初対面のホームレスを好きになる女の子がいるのか。
そんなことを悶々と考えていると、ラーメンを食べ終えたらしい女の子が「ご馳走様でした」と合掌した。銀司も残った汁を全て飲み干すと連れだって屋台を出る。ラーメンを食べている間は何処かへ失せていた寒気が途端に舞い戻って来た。
「ラーメン、ありがとうな」
「いいえ、気にしないで下さい」
言いながら女の子はチラッと銀司の顔を見遣った。何か言いたそうな表情をしている。ひょっとして、自分の顔に何かついているのか?
「……どうかしたかい?」
「えっと、あの……もう少し付き合って頂けませんか?」
どうやら顔に何かついていたわけではないらしい。予想は大きく外れて、更なるお誘いを受けた。銀司は一瞬黙り込んだが、この際もうどうにでもなれと大きく頷いた。
「ああ、いいよ」
「本当ですか! ありがとうございます!」
女の子はパッと表情を明るくしたかと思うと、最初と同じように銀司の腕を引っ張って歩き始めた。
以上です。
このあとは驚きの展開と結末がまっています。
続きはこちらから。
途中までなのでおもしろいも何もないかもしれませんが、もしよろしかったらシェアしてください。